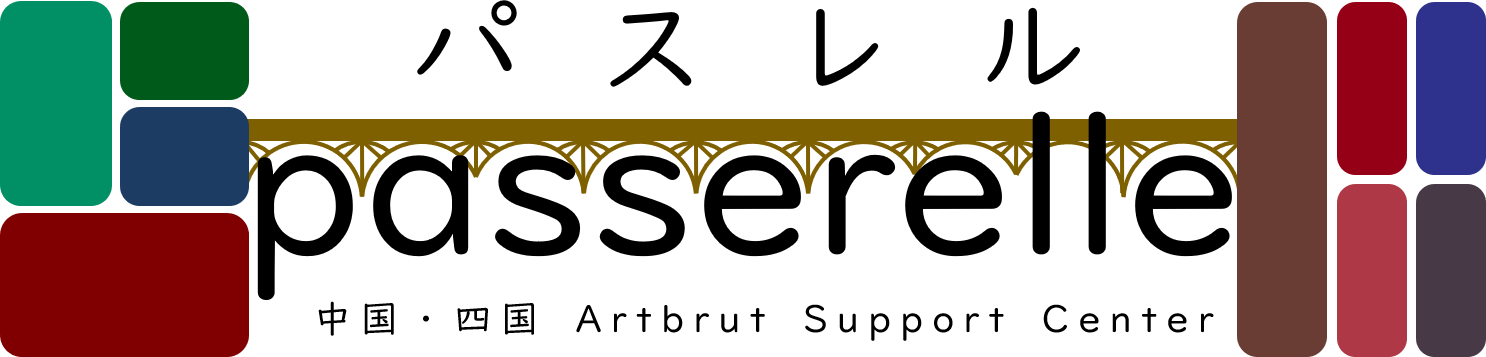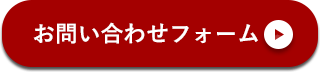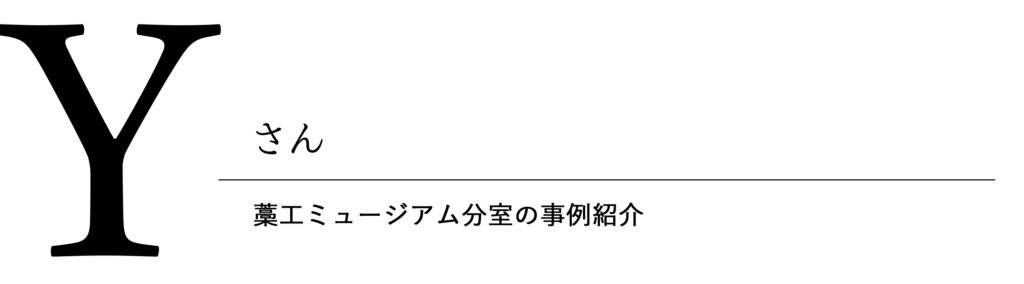![]()
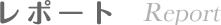
現場を巡る対談 vol.4
作成日時:2024年4月25日
報告者:松本志帆子(藁工ミュージアム分室)
演劇公演「祝祭 音楽劇 小さな星の王子さま」の出演者やミュージシャン、スタッフたち出演者には、身体など目に見える障害のある人や聴覚など一見わかりにくい障害のある方、弱視ほか手帳はないが配慮が必要な方、0歳児の母などがいた。年齢や職業、生活環境など十人十色で、この事業がなければ日常では出会わなかったかもしれない人たちが集まった。
[事例経過]
出演者の多くは演劇経験がなく、動機は様々で、お芝居を一度やってみたかったという方もいれば、障害のある人と一緒に作品作りをしてみたかったという人、自分の中にある壁を乗り越えたい人など様々だった。また、ミュージシャンやスタッフは障害のある人たちと一緒に作品づくりを行うのは初めてだった。
大半が初めての創作現場では、「障害者」=「支援される人」、「健常者」=「支援する人」ではなく、その時々に現れる何かしらの壁を乗り越えようと共に向かい、よい作品に向かうことだけにただ励まし合い、対等に存在していた。ここで生まれたよい関係性は作品づくり以外での交流も自発的に生み出している。着物を着る会を行ったり、聴覚障害のある方がやっている手話カフェに参加したり、誘い合ってミュージシャンのライブや観劇に行ったりと、それぞれの行動範囲を広げた。そしてその交流は定期的に続いている。
[取り組みの内容]
年齢や性別、障害種別や程度、経験の有無を問わず出演者を公募し、障害のある人を含む様々な個性を持つ人たちとともに「星の王子さま」(原作:サン=テグ・ジュペリ)の演劇作品をつくり、上演した。
[まとめ・今後の展望]
この事業を通じ、内にある目には見えない壁を乗り越えたり、新たな気づきを得たり、何らかの変化を感じたというアンケートを大半の人から得た。文化芸術活動は新たな交流を生み出し、それぞれの固定観念や世界を広げ、生活を豊かなものにしてくれるとともに、個々の違いや存在が対等に認められ誰もが生きやすい社会形成につながるものだと改めて実感する事業だった。今回の事業で十分ではなかった鑑賞支援など反省点を踏まえ、今後も事業に取り組んでいきたい。
【現場を巡る対談】
話し手:松本志帆子
(藁工ミュージアム分室)
西木正
(徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター)
渉秀之
(アートベースしまねいろ)
土谷享
(パスレル)
聞き手:岡村忠弘
(パスレル)
障害の有無を乗り越え、対等な関係性を醸成した演劇公演
松本 2021年の夏に演劇公演を行ったんですけれども、その出演者と、出演者だけではなく関わったスタッフや、音楽劇だったのでその際のミュージシャンの方とかの変化というものを事例として紹介させていただきたいと思って報告書にあげました。
この演劇公演は、本来は一昨年の2020年2月に公募をしてその夏に上演する予定だったんですが、公募を終了した直後にコロナ禍になり中止せざるをえないという判断になって、1年以上にわたり出演者が離れていかないようになんとかオンラインとかで稽古を続け、ようやく本番を迎えました。
出演者の中には身体障害とか目に見える障害のある方もいたんですけれども、聴覚に障害がある方もいましたし、病気で本当は片方の耳が聞こえないけれども自分は障害者だと言っていない方や、弱視の方だったり、手帳は持っていないグレーな配慮の必要な方もいましたし、妊娠と出産を経て公演に出演するという方もいたり、サポーターも含めとにかく色んな人がいらっしゃいました。当初スタッフとして関わっている演出家だったり俳優というのはどうしても障害のある方のサポートをする、支援をする人というイメージで関わっていたんですが、作品を作っていく中で、スタッフの方が障害のある方に支えられていると後になって気づくということが多々あったり、聴覚に障害のある方が音のきっかけがわからないのをどう解決するのかということをミュージシャンの方も一緒に考えたりとか、そういう本当に対等な関係性というのが演劇公演を通じて生まれていたと思いました。また、障害のある方というよりは健常者の方が大きな気づきがあることが多くて、自分たちの考え方を変えていかなければいけないんだな、というような内面的な変化があったので、それを事例経過として書いた次第です。
この舞台を通じて、ふだん福祉事業所や学校の友達としか出会わない障害のある方たちが、今まで出会ったことのない属性の人たちに出会うことができ、新しい日常を開くことができました。
たとえば、障害のある出演者の中に100円ショップの「ダイソー」をよく利用する方がいたんですが、その方は「セリア」は知らなかったんですね。演劇の小道具を探していた時に、別の出演者の人が「それ、セリアにありましたよ」と言ったところ、「セリアってなんですか」という話になり、その方は以来セリアによく行くようになったそうなんです。また、身体に障害があると着物を着るというのはなかなかハードルが高かったんですが、着物がとても好きなスタッフが「大丈夫大丈夫、簡単に着られるから」と簡単にできる着方を一緒にやる会を公演終了後にやったりとかもしました。
小さいことかも知れないけれど、そういったところから行動範囲が広がっていったり、交流が自発的に生み出されていって、しかもそれが舞台が終わった今も定期的に続いていて、彼らの日常の世界がぐっと広がっていったんです。日常の行動範囲や交流が広がるということは、イコール生活が豊かになるとか、その人の人生が広がるということ、豊かになるということなので、この事業は大切な事業だなと改めて思いました。
障害者芸術文化活動支援普及事業の意義
ー 1事例だけではなくて、この事業を通して変わった支援者やスタッフ、障害当事者のことを変化した点として書いてくださっていたんですね。この事例にしようと決めた理由はありますか。
松本 「この事業の意義」というところにつながると思うんですけれども、私は、この事業は「障害者」という言葉はついているけれども障害者だけのための事業ではないと思うんです。世界中に生きている人がいて、しかもそれぞれみんな違うわけです。その違いをおもしろがれたり、認められたら、もっと生きやすい社会につながるんじゃないかと思います。それをまずは障害のある方から取り組んでいこうというのが、障害者芸術文化活動の意義でおもしろさなのではないかなと思うんですね。
なので、先ほど話した障害者の方の事例だけではなく、障害のある人の変化が別の健常者といわれる人の変化にも繋がっているということと、障害者という手帳を持っている人だけに特化するのではなく、手帳を持っていないグレーの方って本当に世の中にたくさんいると思うんですね。だからそういう人たちも一緒に巻き込んでいくというか、そういうことがこの事例で伝えられたらいいなと思って、具体的な固有名詞とかはないんですけれども、書いた次第です。
ー 言葉にするのは簡単なんですけど、昨今いわれている共生社会の縮図が松本さんの報告の中にはある。無理矢理ではない、誰しもが温かい共生社会というものがあるなあと思って聞かせていただきました。僕ばっかり質問するのもあれなんですが、これは最終的にはお互いが配慮しつつ気づき始めたみなさんがいると思うんですけど、これはその舞台演劇だからこそ気づけたみたいなものがあるのか、これがたとえば別にスポーツイベントでも良いのかとか、松本さんどう思いますか?
松本 舞台芸術だからこそだと思いますね。スポーツは勝負になってしまうんですが、舞台芸術は競争ではないんです。演劇には、まず舞台に立つ俳優さんがいる。だけど、それを作るためには演出家や脚本家もいて、大道具や小道具を作る人もいなければいけない。さらには、舞台の動線を考える舞台監督、ミュージシャン、照明、その他いろいろな人が関わっている…というのがすごく大きいんじゃないかなと思います。美術は美術でもちろんまた良さがあるわけですが、今回は演劇作品だったからこそ、それぞれが歩み寄るというか。すごくしんどくて、もうお芝居は二度と嫌だという人もいるんですけれども、現場は楽しかった、だから終わってからも交流が続くという、不思議な世界ですね。
ー 広島の保田さんが出してくれた事例で、車椅子で生活されていた方が舞台演劇をやってみたら、目標にしていた一人暮らしを始めたというものがありました。もし僕らが舞台演劇をするとして、たとえば僕に役が与えられたとしたら、やっぱり最初はちょっと恥ずかしかったり、声がうまく出なかったりすると思うんです。でも、そこを乗り越えた時にもう一つの自分がうまれるというか、なにかそういう力のようなものが舞台芸術にはあるのかなと思いました。確かにスポーツは個々に競い合うみたいなところがあるんですが、そういうところではなくて、舞台は支え合う、そして一歩踏み出させるような力があるんでしょうかね。
関係者のネットワーク作り
渉 いま、島根県内で演劇の方たちとのネットワークがあるかというと私自身にはないんですね。もし島根県でも舞台演劇を考えた企画をやろうと思った時に、ネットワークがゼロなわけです。広島の保田さんにしても、藁工ミュージアムさんにしても演劇ということは背景にもともとそのような要素、ネットワークがあって企画されたものなんでしょうか?
松本 藁工ミュージアムの場合は、同じ敷地内に別のNPOが運営する「蛸蔵」という多目的ホールがあって、そこには演劇活動をしている人たちがいたんですね。ミュージアムが開館してから10年くらいたっているんですが、その前から演劇の活動をしている方たちはもう20年以上活動していて、ミュージアムは蛸蔵よりずっと新参者なんです。だから、まずは演劇の人たちと仲良くならないとなと思って、演劇公演があったら必ず観に行ってまず顔を覚えてもらうということをしていました。
この普及支援事業が始まった時、最初は美術から始めたんですが、せっかく同じ場所に演劇をしている人たちがいるわけだからその人達と一緒にこの事業をやっていけば美術と舞台芸術を混ぜることができると思いましたし、アートの中でも分野が違うと交流が一切なかったりもするので、そういったネットワークというか交流の幅を広げていけば、どんどん世界が豊かになるだろうなと考えて、蛸蔵の演劇をしている人たちに相談をするようになりました。
この演劇公演自体は5年くらいかけて実施しました。一番最初は、演劇の人たちも障害のある人たちと日常的に接したことがない。そもそも一緒にお芝居ができるんだろうかという不安もあるし、知らないものと一緒に何かをするというのもけっこう怖い。いきなりおもしろい!とは思えないので、最初は盲学校とか聾学校に行って演劇の手法を使って遊ぶワークショップをしてもらえませんか?というところから始めて、鳥取県にある「鳥の劇場」の中島諒人さんにじゆう劇場の話を聞いたり、埼玉県の「キラリ☆ふじみ」という劇場で芸術監督をしていた多田淳之介さんから学んだり、2~3年かけて演劇の人たちと一緒に学びながら演劇公演をしようと進めていきました。
たぶん広島の人たちもやろう!といっていきなりやったのではなく、徐々に計画を立てて1年目はこれやって、2年目はこれやって、というふうにやってきたから今も続いているんじゃないかと思います。
渉 ありがとうございます。思い切って3年、4年と時間をかけながら、舞台演劇にも関心を持つのも大切ですね。
西木 センターも最初は美術から取り組んでいきまして、2年目、3年目でしたかね、舞台芸術もということで、徳島の伝統芸能、阿波おどりをみんなでやるというようなことを開いたりとか、そんなことを取り組んでいたんですが、コロナ禍でなかなか新しいことができなくなってしまいました。それで今年度、徳島県文化振興財団から声をかけていただいて、何年かの計画でリージョナルシアター事業を取り組んでいこうとしているところです。ご指導いただくのは北九州出身の有門正太郎さんという方なんですが、この方とも先日お会いして打ち合わせをしたり、施設を見学したりしていまして、ゆっくり進めていけたらいいなという話をしていたところです。今年1年間で何らかの成果を得るというものではなくて、藁工ミュージアムのように細く長く続けていって何かを見つけていけたらいいなと言うようなスタンスでやっていきたいと思っています。
舞台芸術のもつ「力」
―土谷さんはこの事例を通しての話はありませんか?
土谷 はい、素晴らしい話で。僕もその、演劇人が縦割りできちっきちっと役割が決まっているという良さと、そこでの組織としての固さがあって、僕は苦手な世界なんですけども、こういった外界というか今まで関わっていなかった障害者手帳を持っているような人たちとか、社会の中でなにか課題を抱えている人たちと一緒に取り組むという、お互いに新しさへ踏み出すことによって、その演劇の良さっていうのは豊かさに変わっていく素晴らしい事例だなと思いました。
ー 脳損傷友の会高知青い空にはB型事業所があるんですが、問題行動のある方をB型事業所の枠にはめてしまいがちなところがあるんですよね。「~したらだめだよ」とか「~しないようにしましょう」と言ってしまうことが多くて、その方達にスポットライトが当てられることが少ないわけです。でも、演劇をやれば、役をもらったりしてその方に注目が集まったり輝く瞬間があったりするわけで、うちの事業所でも演劇のテイストを取り込んで、そういう感覚を得る機会を利用者さんにも持ってもらいたいという気持ちが生まれつつあります。簡単に言えばうちの事業所で舞台演劇を取り組んでみようよとか、舞台演劇が持つ役割、意義みたいなものをもう少し日常生活に拡大解釈をしたりして活かせないかなと思っています。
松本 人間って、日常生活の中で「演じて」いると思うんですね。職場で働いているときの私と家でいるときの私は、やっぱり違います。それは演じ分けているわけではなく、自然と切り替えられているんですけど。岡山県で活動している菅原直樹さんという演劇の方がいて、「OiBokkeShi(オイボッケシ)」という名前で活動しているんですけど、「OiBokkeShi」というのは、「老い」と「ボケ」と「死」のことで、90歳を超えたおじいちゃんと二人でお芝居をやっています。菅原さんご自身は介護福祉士で、介護の仕事をしながら演劇をやってらっしゃいます。介護で認知症の方と対峙したりする時に日常で切り替えているというものを応用していくと介護をする人もされる人も生きやすくなるんじゃないか、というのをワークショップでやったりしているんですが、事業所の中でけっこう活用できるんだろうなと思って。菅原さんのワークショップを一回職員の方が受けるだけでも変わるかもしれませんし、「今日はこれをやりきる人ね」って演じていくと、職員の人も、働く利用者の人もその日一日楽しく過ごせていいかもしれないなと思いました。
ー 演じることで生活の中とか支援の中に組み込んでいければ、さまざまな感情も消化できるんじゃないかと、舞台演劇にはそんな力があるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。
※この対談は、令和3年度障害者芸術文化活動普及支援事業の一環として行われたものです。